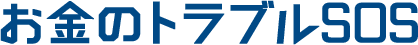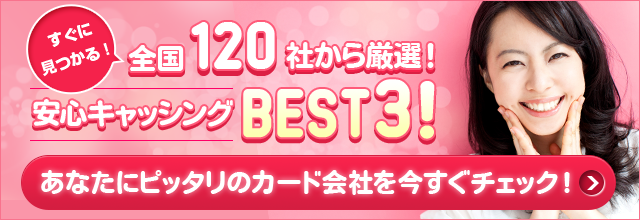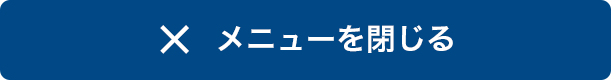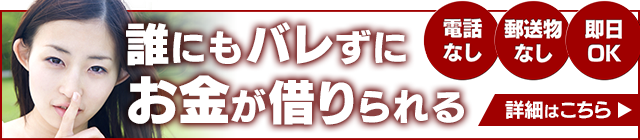免除しても年金がもらえる!?国民年金保険料免除申請の内容とやり方
国民年金保険料の納付は、加入者の義務となっています。
しかし、収入が少なかったり、失業などで「どうしても保険料が納められない…」という人はいらっしゃると思います。
そんな時はどうすればいいのか?
実は、経済的に納付が難しい人は未納のままにせず、「保険料免除制度・納付猶予制度」を利用することで将来もらえる受給額が断然お得になるんです!
この記事では、そんな国民年金保険料免除制度について、制度の内容や必要書類・手続き方法や手続きの流れを詳しくお教えします。
支払いが厳しい人は免除できる?国民年金保険料の免除制度とは
国民年金の保険料は収入が少ない、失業してしまったなどの理由で払えない人のため、「保険料免除・納付猶予制度」、「学生納付特例制度」というものがあります。
基本1年ごとに保険料免除や納付猶予の申請をする制度ですが、過去に滞納している期間があった場合、2年1ヶ月以内の期間分であれば遡って申請をすることも可能です。
では、どんな制度なのかそれぞれ見ていきましょう。
保険料の納付が免除される、「保険料免除制度」
「保険料免除制度」は、国民年金保険料を納付する本人が申請書を提出すれば、申請後の審査結果によって保険料納付が免除されるというものです。
保険料免除制度の最大のメリットは、免除申請をすれば保険料を払っていなくても年金の受給資格期間に算入され、ある程度の年金がもらえるという点です。
免除される金額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4つに分かれています。
どれぐらい免除されるかは申請する本人の前年度の所得によって決まり、また親等の世帯主、配偶者がいる場合はこの中で最も所得が高い人が審査対象になります。
ただし、失業時には少し条件が異なり、本人の収入は自動的に0とみなされて、世帯主・配偶者のうちどちらか前年度所得の高い人が審査対象になります。
保険料の納付が猶予される、「納付猶予制度」
本人、または配偶者の所得が一定額以下であれば、免除申請同様に申請書を提出することで、保険料の納付が猶予されます。
これは「納付猶予制度」と言い、平成28年6月までは20~30歳未満の方限定の制度でしたが、平成28年7月以降からは20~50歳未満の方と制度を利用できる年齢の幅が広がりました。
申請者本人が失業している場合は、猶予申請も免除申請同様、配偶者の前年度所得のみが審査対象となります。
もちろん猶予制度は免除とは違うので後で保険料を収める必要はありますが、お金が少ない時に無理して払わなくていいのはありがたいですね。
【関連記事】
学生限定の納付猶予制度、「学生納付特例」
また、大学や専門学校等の各種学校に在籍している学生の方は、「学生納付特例制度」というものを利用することが出来ます。
こちらも納付猶予と同じく納付を先送りに出来る制度ですが、審査対象となる所得は本人のみであり、アルバイトなどで相当稼いでいない限りは受けることが出来ます。
対象となる学校も大学や短大、専門学校、高校等の他に夜間・定時性課程や通信課程等も含まれるのでたいていの学生の方が対象となります。
自分の通う学校が対象となるか不安な方は、日本年金機構の公式ホームページの「学生納付特例対象校一覧」より確認をしてみましょう。
学生納付特例制度が利用できる方は学生納付特例の申請が優先され、通常の保険料免除や納付猶予の申請はできません。
支給額がこんなに違う!「未納」と「免除」・「猶予」の違い
では、「免除」・「猶予」は「未納」の状態とどう違うのでしょうか?
まず「免除」と「未納」は、先ほどもお伝えしたように、保険料を払わなくても年金がもらえるという点で大きく違います。
支給される年金額は免除された保険料の割合によっても異なりますが、以下のようになります。
| 全額免除 | 平成21年度4月以降は、全額納付した場合の老齢年金の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給される |
|---|---|
| 4分の3免除 | 平成21年度4月以降は、全額納付した場合の老齢年金の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給される |
| 半額免除 | 平成21年度4月以降は、全額納付した場合の老齢年金の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)が支給される |
| 4分の1免除 | 平成21年度4月以降は、全額納付した場合の老齢年金の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)が支給される |
これだけでも、未納より免除のほうがお得なのが分かりますね。
そもそも年金を受け取るには受給資格期間というものがあり、公的年金制度への加入が10年以上なければ受け取れません。
未納のままではこの受給資格期間に算入されませんが、保険料免除はもちろん、納付猶予や学生納付特例もこの受給資格期間に数えられます。
そのため、ただ払わないよりはきちんと申請をした方が、老後の年金を受け取れる可能性が増えるのです。
また、年金は老齢年金だけでなくケガや病気による障害や死亡といった不慮の事態が発生した際に受け取れる、障害年金や遺族年金もあります。
未納の状態では障害年金や遺族年金を受け取れない可能性がありますが、免除・猶予の申請をしておけば障害年金も遺族年金も受け取れます。
「年金をもらうなんてまだまだ先の話」と思っているかもしれませんが、万が一の時、通常であれば受け取れるはずの援助がもらえないのは困りますよね?
さらに、未納のままでいると、預金等の財産を差し押さえられる可能性もあります。
保険料を支払うことが難しい方は、とりあえず年金事務所や役所に相談をし、保険料免除か納付猶予の申請をしておいて損はないでしょう。
年収によって免除額が変わる。保険料免除・猶予制度の所得条件とは
保険料免除や納付猶予を受けるには、申請する期間の前年度の所得が一定額以下であることが条件となります。
免除の申請の際は申請者本人、結婚されている方は配偶者、両親と同居しており親が世帯主の方は世帯主、この中で最も前年度の所得が高い方が所得条件の審査対象者となります。
納付猶予の申請では、本人と配偶者、この中のどちらか前年度の所得が高い方が所得条件の審査対象者となります。
また、学生納付特例の申請では本人の前年度所得のみが審査対象となります。
それぞれの免除・猶予を受けられる所得条件は下記のようになります。
| 全額免除 | 申請期間の前年度所得が、以下の金額の範囲内である (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
|---|---|
| 4分の3免除 | 申請期間の前年度所得が、以下の金額の範囲内である 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 半額免除 | 申請期間の前年度所得が、以下の金額の範囲内である 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 4分の1免除 | 申請期間の前年度所得が、以下の金額の範囲内である 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
| 納付猶予 | 申請期間の前年度所得が、以下の金額の範囲内である (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 |
| 学生納付特例 | 申請期間の前年度所得が、以下の金額の範囲内である 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等 |
この他、生活保護を受けている方や、障害基礎年金・被用者年金の障害年金障害年金を受けている方はもちろん、その他の理由で保険料の納付が困難と認められる場合等も免除を受けられる可能性があります。
自分が免除対象者か分からない方は、一度電話でもいいので年金事務所等に問い合わせてみてください。
国民年金保険料の免除申請に必要な書類と申請のやり方は?
自分が免除・納付猶予申請の対象者か確認できたら、申請をしましょう。
学生納付特例は、免除・納付猶予申請と少々勝手が異なるので後で説明をします。
まずは、免除・納付猶予申請の場合ですが、必要書類は変わりませんのでまとめて説明します。
申請時期は、基本的にいつでも申請可能です。
申請をすれば7月~翌年の6月まで、最長1年間保険料の免除、もしくは猶予を受けることが出来ます。
ただし、7月1日以降も継続して免除・猶予を受けたい場合は再度申請をする必要があります。
では、申請方法ですがこれは必要書類さえキチンとそろえれば、さほど難しい手続きでもありません。
STEP1.必要な書類をそろえましょう
申請するのに必要な書類は以下の3つです。
- 免除・納付猶予申請書
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 運転免許証等の本人確認書類
申請書は役所の窓口でもらうか、日本年金機構の公式ホームページからダウンロードすることができます。
また、1枚の申請書で申請できるのは1年分だけですので、過去の分もまとめて申請したいという人は申請したい年数に合わせて申請書を用意してください。
年金手帳を失くしてしまった、基礎年金番号も分からないという場合は年金事務所に行けば教えてもらえますし、手帳の即日再発行もしてもらえます。
また、失業・廃業等で免除・猶予を受けたい方は以下の書類も必要です。
- 雇用保険受給資格者証、または雇用保険被保険者離職票等いずれかのコピー
- 個人事業の開廃業等届出書、または事業廃止届出書いずれかのコピー等
雇用保険受給資格者証、または雇用保険被保険者離職票がない場合は、最寄りのハローワークで雇用保険資格喪失確認通知書を発行してもらう必要があります。
家族の扶養に入っていた等で雇用保険に入っていなかった場合、退職証明書等でも問題ない場合も多いので、まず申請予定の窓口に確認をしてください。
特に失業等で申請をしたい方は用意する書類が、雇用保険加入・未加入、会社員・個人事業主等で変わってきます。
2度手間を防ぐため、予め電話で必要書類を確認してから申請することをオススメします。
STEP2.申請書に必要事項を記入しましょう
申請書には氏名・住所等の基本情報から、前年度所得、確定申告の有無など様々な記入欄があります。
申請書の中に希望する免除等区分について確認欄がありますが、この部分は基本記入せず、以下の順番で優先的に審査され、その中の該当区分が適応されます。
- 全額免除
- 納付猶予
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
もしこの中で審査を希望しない免除区分がある場合は、該当する免除等区分の該当する数字を「×印」で消しておけば、その区分は飛ばして審査されます。
例えば免除を希望しており、納付猶予になると困る、もしくは希望しない方は納付猶予に×印をつけて提出すれば、「全額免除」→「4分の3免除」と納付猶予を飛ばして審査がされるわけです。
詳しい記入例は、日本年金機構の公式ホームページにも載っていますし、同じページに書き方を解説した動画もあります。
1つ1つの記入項目に対して丁寧に説明してくれているので、何を書けばいいか分からない時には是非確認をしてみてください。
また、「ねんきんネット」を使って、パソコン上で申請書を作成することも出来ます。
必要項目を入力した後、印刷用ファイルをダウンロードし印刷をすれば、署名欄に署名、または捺印をするだけで作成できます。
手書きよりパソコン入力の方が得意な方は試してみてはいかがでしょうか?
STEP3.申請書等を提出しましょう
必要書類をそろえ申請書も記入し終わりましたら、住民票をおいてある市区町村の役所の国民年金担当窓口か、年金事務所へ提出をしてください。
必要書類はSTEP1で紹介した物になりますが、手続きに行くついでに窓口で書類をもらってその場で記入するという方は、申請書に印鑑、もしくは本人署名をする欄があるので念のため印鑑も持って行くようにしましょう。
なお、「忙しくて平日窓口に行く時間がない!」という方は郵送でも申請可能です。
その際は、申請書を必要書類と共に市区町村の役場へ郵送してください、
STEP4.審査結果を待ちましょう
提出後、約2~3ヵ月後に審査結果が郵便で送られてきます。
その間、保険料を滞納していいた方には保険料納付の催告状等が届く場合もありますが、その際は結果が出るまで払わずとも問題ありません。
ただし、申請が却下となった場合や一部免除となった場合は、審査後決められた保険料を納付する必要がありますので忘れないように注意してください。
その他.学生納付特例の申請方法は?
学生納付特例の申請方法や提出先は、基本的に免除・納付猶予申請を変わりません。
ただし、以下のように用意する必要書類や申請書が変わるので注意しましょう。
- 学生納付特例申請書
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 運転免許証等の本人確認書類
- 在学期間が分かる在学証明書(原本)や学生証(コピー)等
学生納付特例の申請手続きは、在学中の学校等でも出来る事があります。
気になる方は在学校の事務に尋ねたり、日本年金機構ホームページの「学生納付特例対象校一覧」の「代行事務」欄を確認してみてください。
学生納付特例は承認された場合、4月~翌年3月までの最大1年分の納付猶予を受けることができ、猶予期間が通常の納付猶予とは異なります。
こちらも翌年4月以降も学生納付特例を継続したい場合は、再度手続きが必要になります。
免除しても「追納」すれば全額もらえる!保険料の追納について
免除申請をすれば保険料を納めずとも国民年金はもらえますが、受給額は減ってしまいます。
さらに、猶予申請や学生納付特例は支払いが猶予されただけなので、こちらは後から収めなければ払わなかった期間分の年金をもらうことが出来ません。
そのため、保険料免除・納付猶予・学生納付特例申請をした方は10年以内であれば、後から「追納」して老齢基礎年金の受給額を満額にすることができます。
追納をする際は、年金事務所への追納の申し込みが必要です。
追納は1年分だけでなく2年分等まとめて納めることも可能で、追納申込書を年金事務所へ提出すると追納用の納付書がもらえ、金融機関や郵便局、コンビニ等から支払うことができます。
しかし、追納する際は免除・猶予申請をした期間の翌年度から3年度目以降には、承認を受けた当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされるようになります。
また、追納ができるのは承認をされた期間のうち原則古い期間からの納付となります。
例えば、5年間免除等を受けていて追納する際、加算額が掛からない最近の免除期間から払いたくても、払えるのは加算額がかかった5年目から、となるのです。
その為、保険料の追納をする際は加算額がなるべく少なくなるように、早めの追納をオススメします。
追納した保険料は全額「社会保険料控除」の対象になり、多少なりともお金が戻ってくるので、追納したら年末調整や確定申告などでしっかり申告をしておきましょう。
追納しておけば、将来的に受け取る年金額が免除時より増えますので、余裕が出来たら追納をするようにしたいですね。
国民年金保険料免除・猶予申請のポイント!
最後に、免除・猶予申請についてのポイントをまとめておきます。
- 保険料免除は、本人・配偶者・世帯主(失業者の場合は配偶者・世帯主)のいずれかのうち一番年収が高い人の前年度所得により、免除の割合が決まる
- 納付猶予は、本人・配偶者(失業者の場合は配偶者のみ)のいずれかのうち一番年収が高い人の前年度所得が一定額以下であれば、保険料納付の猶予を受けられる
- 学生納付特例は各種学校に在学中の学生であれば、本人の前年度所得が一定額以下の場合、保険料納付の猶予を受けられる
- 過去2年1ヶ月まで遡り、免除・猶予申請をすることができる
- 申請が通った際、免除・猶予される期間は7月~翌年6月までの最長1年間、学生納付特例は4月~翌年3月の最長1年間です
- 免除・猶予申請が通っても年金を満額もらいたい方は加算額が少ない、もしくはかからないうちに早めに追納をしましょう
免除・猶予申請に通れば、未納でいるより老後の年金はもちろん、万が一の時でも年金を受け取れるようになります。
現在、保険料の納付が難しい状態にある方は、ひとまず年金事務所か役所の国民年金担当窓口へ相談をしてみてください。